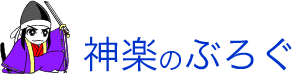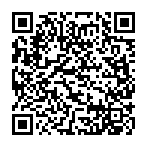5月4日に浜田市で、西村神楽社中結成30周年記念の石見神楽公演が行われました。行ってみて、まず会場の大きさにびっくり。「海の見える文化公園」の野外劇場という場所なんですが、本当に広い!

まずは「塩祓」で、じっくりと舞を見させていただきました。女性の方が二人で、四方への舞をされました。他の演目だとたいてい一方だけですから、東西南北の4回としっかり基本の舞を見ることができました。そして続く「八幡」、こちらも女性の方が舞われました。鬼の方はとくにセリフがよかったと思います。しんどそうなのも伝わってきましたが、迫力ある低い声で鬼を表現されていました。


子供神楽の「道返し」「塵輪」は、舞の上手さは本当に素晴らしいですね!またそれ以上に奏楽も素晴らしいんです。特に笛がすごいなぁと思いました。音だけ聞いたら大人と言われてもわからないくらいお上手でしたよ!手打ち鐘のほうは、なかなか苦労していた子


「四神」は、名前だけ見たら「五神」と似ていますが、こちらは特に深い意味もなく、熟練の四人の舞手さんによる神楽、というのが正しい見方かな、と思いながら見ました。「天神」は何と言っても立ち合いの緊迫感がたまりませんね!これだけ息の合った立ち合いは、広島ではなかなかお目にかかれないと思います。「八街」(やちまた)も広島ではなかなか見れない演目ですが、こちらは子供神楽で舞われていました。宇津女命と猿田彦が出てくる演目で、少し地味かもしれませんがとても面白い神楽です。


今回一番面白かったのが「頼政」でした。実は一番期待していたのですが、期待以上の面白さで大満足!お猿さんの活躍というかいたずらは、見る人をも巻き込んで上へ下への大騒ぎといった感じで、飽きることなく楽しませていただきました。一番大きなお猿さんが太鼓の上に居座り、貫禄たっぷりで他のお猿さんの動きを見ているのも、リアルでよかったですね。また武器を取られた頼政さんが、なんとか奪い返そうとするも、なかなか刀を返してくれなかったところは笑わせてもらいました。


オーソドックスな「塵輪」と「鍾馗」ですが、こうして続けて見ると違いがよくわかったりして勉強になりましたね。特に「鍾馗」は他の演目に比べて、ちょっと楽のテンポがゆったりしていると思いました。それだけ舞が重厚で力強い感じがして、まさに「鍾馗」にピッタリでした。そして「黒塚」は1時間以上の大熱演!でっち小僧さんが二人していろいろ笑わせてくれました。客席に降りた悪狐も、一番後ろまで行ってみたり、そうかと思えばいつの間にか天蓋に小僧さんがいたり

しかし残念なことに、事情によりここで帰らないといけませんでした。
この記事が面白い・勉強になったと思われたら迷わずクリック
2007,05,05 Sat 12:36
コメント
KAOさん、コメントありがとうございます。
天気もよくて実に盛大なイベントになりましたね!
見ていてパワーをもらったような気がします。
これからも、広島だけでなく、石見地方の神楽をたくさんご紹介していきたいと思います。
大変お疲れ様でした。
またコメントお願いします☆
天気もよくて実に盛大なイベントになりましたね!
見ていてパワーをもらったような気がします。
これからも、広島だけでなく、石見地方の神楽をたくさんご紹介していきたいと思います。
大変お疲れ様でした。
またコメントお願いします☆
| 特派員 | EMAIL | URL | 07/05/06 08:17 | BFfnvy1Y |
「神楽のぶろぐ」への掲載ありがとうございます。
このイベントは、「30年間支援していただいた地元の方・ファンの方々にお返しを」という目的で開催されたものでした。当日は天候が微妙でしたが沢山の方に集まって頂き盛会に終える事ができました。
また新しい一歩を社中として歩んでいかなくてはなりませんね。
特派員さん、合わせて石見神楽のPRありがとうございます。浜田はもちろん、益田・江津等々石見神楽の盛んな地域がたくさんあります。みなさん、ぜひ石見地方にも足をお運びください☆
このイベントは、「30年間支援していただいた地元の方・ファンの方々にお返しを」という目的で開催されたものでした。当日は天候が微妙でしたが沢山の方に集まって頂き盛会に終える事ができました。
また新しい一歩を社中として歩んでいかなくてはなりませんね。
特派員さん、合わせて石見神楽のPRありがとうございます。浜田はもちろん、益田・江津等々石見神楽の盛んな地域がたくさんあります。みなさん、ぜひ石見地方にも足をお運びください☆
| KAO | EMAIL | URL | 07/05/06 02:56 | zy5aLoSc |
コメントする
この記事のトラックバックURL
http://www.npo-hiroshima.jp/blogn/tb.php/117
トラックバック